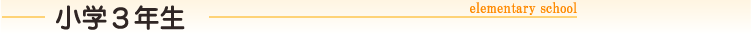
近年教科書の内容が本当に難しくなっています。
以前であれば、小学生4年生で行う授業が
小学生3年生で行われています。
まず、一学期の初めは掛け算なので、
特に問題はないでしょう。
しかし、その次には時計(単位)の問題がでてきます。
半数の生徒さんはここでつまずきます。
そして後に、
小数・分数・三桁の掛け算がでてきますので、
3年生が重要な学年なのがわかります。
当校では、あらかじめ苦手な場所を把握していますので、
その部分を何度も何度も復讐を行います。

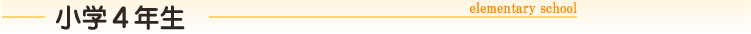
3年生同様に、教科書の内容が本当に難しくなっています。
もちろん小学生5年生で行う授業が
小学生4年生で行われています。
まず、角度の大きさ
これは決して分度器で測るのではなく
直角三角形と直角二等辺三角形の角度を
覚えていなければなりません。
しかし、分度器を使ったばかりの子供たちには
角度は測るイメージがついています。
まずは、それを理解してもらい問題を解き、
慣れてもらいます。 そしてここで、
子供たちの頭を狂わす(単位) cmセンチメートルをmメートルに
kgキログラムをgグラムに Lリットルを mLミリリットル
さらにdLデシリットルに
そして、これに小数も混じってきます。
算数を好きになるか、嫌いになるかは
ここで勝負がつきます。
単位に関しては同じような問題の反復学習が本当に大切です。
当校はその反復学習をたくさん行ってもらいますので、
単位の問題も簡単に解くことができます。

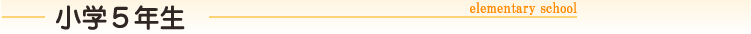
いよいよ、5年生です。
3、4年生同様に、教科書の内容が本当に
難しくなっています。
もちろん小学生6年生で行う授業が小学生5年生で行われています。
5年生は体積を学びます。
ここでは、子供たちの苦手な単位が入ってきます。
3年生・4年生で単位の学習をとりこぼして いた場合
ここで全く歯が立たないようになるでしょう。
そのうえ、小数の割り算・文章題・公約数・公倍数・単位量、
これは中学数学の第一歩ともいえるでしょう。
ゆとり教育の算数とはわけが違いますよね。
このようにとりこぼした算数を取り戻しおかなければ
中学数学は解くことができないでしょう。
当校の反復学習はそのようなとりこぼした勉強をしっかりと補うことができます。

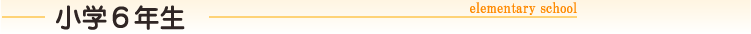
そして中学に進学する一歩前の6年生です。
3、4、5年生同様に、教科書の内容が本当に難しくなっています。
この6年生では、
中学1年生で行う授業が、徐々に行われています。
まずは、線対称・点対称から学びます。
図解が苦手な生徒には、最悪ですよね。
3年生・4年生・5年生で、学んだ勉強が当たり前のように
出題されます。
学習をとりこぼしていた場合、
もう嫌になるでしょう。やる気さえも失われます。
6年生は難題の連続です。
図形が終われば、文字の計算、
そして、分数の掛け算・割り算
さらにまた図形の問題、
拡大図・そして縮図
この縮図は、ほとんどの生徒さんが苦手でしょう。
その次は角柱これには、苦手な単位の計算を使います。
極めつけは、メートル法
今まで算数の点数が80点以上しか取っていない生徒でも
50点くらいまで落ち込んでしまいます。
普段使わない単位に関しては、
本当に反復学習が必要になります。
何問も何問も同じような問題を解きましょう。
反復学習をしていた学生だけが
中学生になったとき、数学が得意科目になります。

鶴見区鶴見塾・鶴見区鶴見個別学習塾・鶴見区鶴見そろばん・「the 塾est」は小学生から中学生まで受験合格を目指す方に
当個別指導the 塾estにしかできない基礎の基礎から発展まで一人一人に適合したカリキュラムで授業を進めていきます。勉強が苦手な方から難関高校を目指す方まで
個人個人のレベルで学習できます。当塾はあなたの将来に少しでも力になりたいと思っています。学費は通いやすい月謝制になっています。